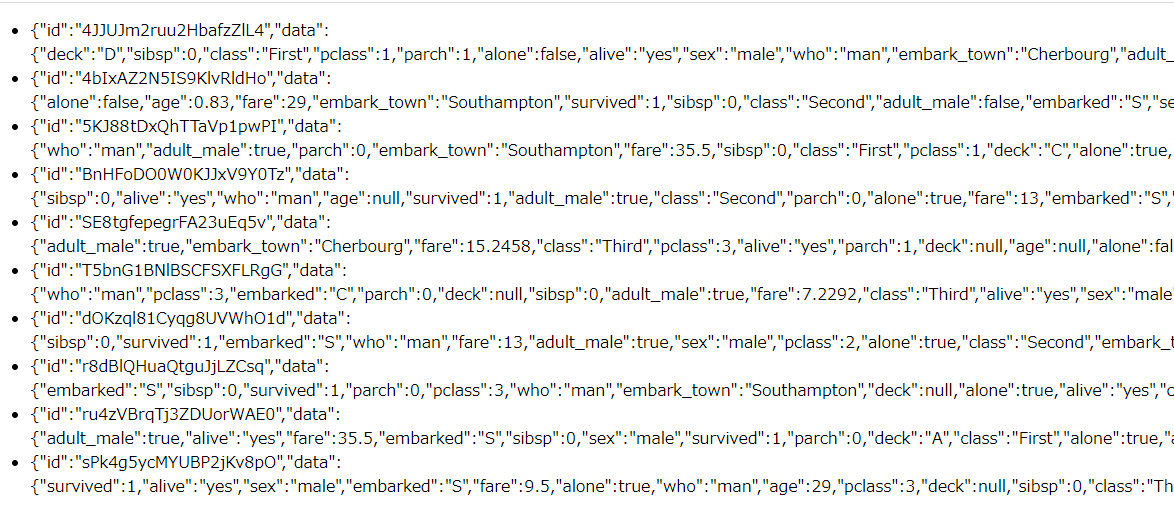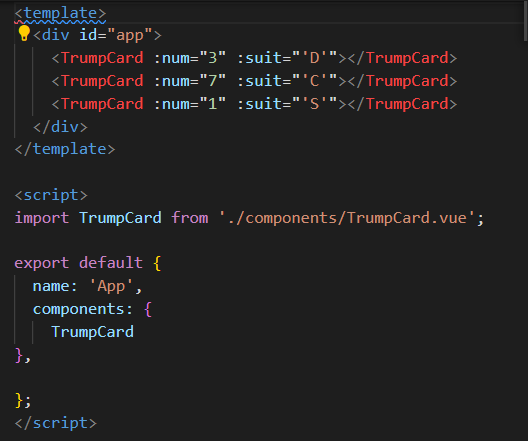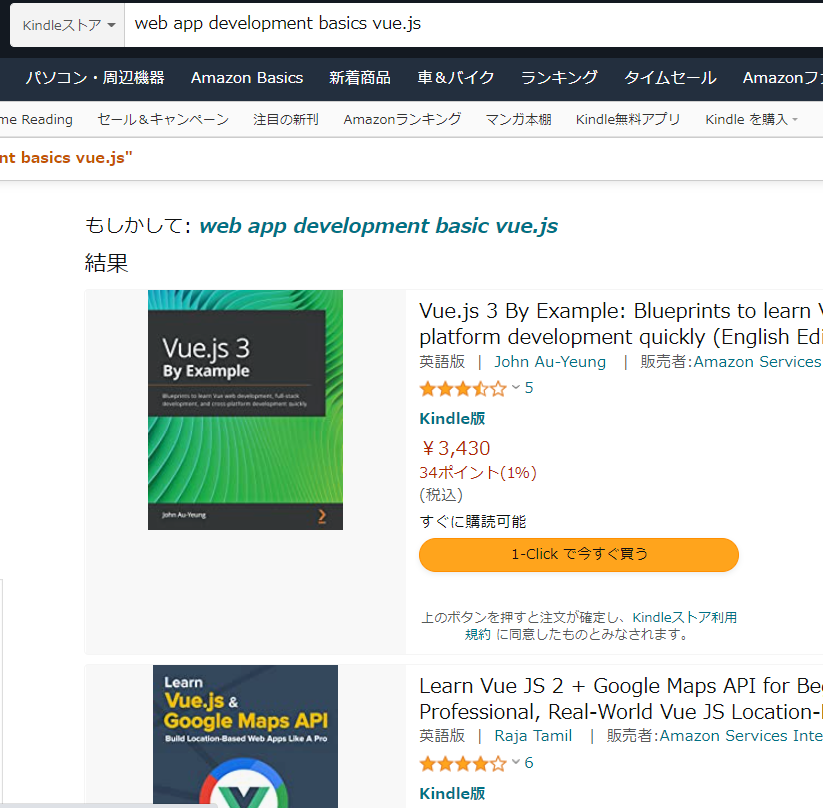ニューズウィーク日本語版の12月28日 1月4日合併号をみてたら、以下の記事を見つけました。
Tokyo Eye の特集記事
これについていろいろ思うことがあったのでまとめてみたいと思います。
教材としての雑誌
記事の概要
著者は、学生時代に背負子(しょいこ)と呼ばれる駅の運搬具を使い、早朝から雑誌を運ぶバイトをされていた苦学生。
その最中に無料で読めていた雑誌の数々は、日本語能力の向上に役立ったと仰っています。
とても嬉しい。
また、雑誌に対する「質の高さ」についても記載されています。
雑誌の記事は、そのほとんどがきちんとした取材や調査に基づいた信頼たる内容で、文章はこなれていて校正もされている。内容はおろか、日本語すら怪しいネットニュースとは一線を画すものだ。
知り合いのなかには、「情報はネットニュース見ればいいじゃないか」と言って何の疑問も持っていない人がいました。残念ですが、日本語が怪しいネットニュースが当たり前になっている世の中になっているのかもしれません。
最後に
衰退が叫ばれる今の日本の雑誌だが、まだまだ存在意義は大きいと思う。ネット情報との差別化を図りつつ、生き残りを測ってもらいたいと願うのは、何もノスタルジックな気分からだけではない。
と締め括られています。
質の高い雑誌が、日本人の日本語力、考える力の源になっているのに、それがなくなるのはもったいなさ過ぎます。それでも、雑誌社の未来は厳しいと思います。
著者のように、室の高いコンテンツを望む方々であれば、ニューズウィークのような雑誌は需要かがあるでしょう。
知識人との戦いでも、ニューズウィークは戦える武器にもなり得ます。
「質の良い」日本語がわからない日本人
でも、日本人の大半は、「質の高い日本語」は求めていません。いや、正確には「質の高い日本語が良い、と気付けない」のかもしれません。
には、様々な日本の子供の言語能力の問題点を見つけてくれていて、そもそも、子どもたちは、文章を正しく読むことすら、できない子が多いらしいのです。そして大人も。
そして、自分が間違って「理解」していることすら気付けない状態です。
こんな状態では、質の高い日本語を提供していても、ごく僅かの子どもたちにしか認識されない雑誌になってしまいます。
今後の対策
ではどうすればいいのか。
すくなくとも、巷のネットニュースと同頻度まで露出して、みんなの目に触れてもらう必要があります。
目に触れてもらわないと、戦いのスタートラインにすら立てないからです。
ここで明るい兆しも見つけました。
実はこの雑誌を見たのはドコモが提供する
dマガジン で見かけたものです。
ニューズウィークを見た理由は「他の雑誌にはない、優れた記事があるのではないか、という期待感から」でした。
店頭で買おうとすると、480円から490円。
それほど高くはないかもしれませんが、「そんな大層な雑誌を買って本当にみるの?
みるの?」という、他人からも、もしかしたら自分自身も思われてしまう雑誌です。
しかし、読み放題サービスでは、気軽に読めます。
この敷居の低さはとても素晴らしいと思います。
それても残る問題点
紙媒体に比べ、格段に手に取りやすくなった状態ですが、それでもまだネットニュースのみを見ている人にとっては、ニューズウィークを手に取ることは少ないと思います。
なぜか。
実際に見てみても、そんなすぐには「質の良い記事」はわからないと思うのです。
実際に読んでみます。
まず最初に「Perspectives」という、漫画で今の世界で起こっていることをわかりやすく説明してくれる記事がでてくるのですが、正直あまりおもしろくない。
まだ新聞のコボちゃんのほうが見る人は多いでしょう。
社会で起こっている問題を鋭く描写していると思うのですが、つかみが弱いかも。。。。
ではどうすればよいか
しかし、このページも含め今後の各記事も、実際に現地の国で取材を行った上、何人もの人が内容をチェックして吟味されたもののはず。
それぞれの記事の内容も確度が高く、日本語の文体や言い回しは、日本人にとっても勉強になるものでしょう。ニューズウィークを見ずにネットニュースばかり見るのはもったいない!
ではどうすれば、ニューズウィークを活用することができるようになるのでしょう。
「ほかの人と話をするときの強力なネタにできる」
ビジネスパーソンであれば、上司や同僚、部下と話をするとき「ニューズウィークで見たんだけど、、、」という枕詞とともに会話をすると、見る目が変わると思います。きっとニューズウィークを見ている人は、日本語版でもそんなにいないはず。
出世や発言力にも影響してくると思います。
主婦や学生についてはどうか。
ママ友、学校の友達に「ニューズウィークでみたんだけど」もいいけど、ちょっとお高くとまった感じがします。
もともとニューズウィーク日本語版は、海外の情報を、国内メディアと異なる視点で冷静に、深く、多角的に捉えることができる、という強みがあるようです。
第一線で活躍するビジネスパーソンや論壇、政府関係者など政財界の要人から高く評価されています
ということで、残念ながら主婦や学生向けには書かれていない模様です。
しかし、最終的に第一線で活躍する人になりたい学生や、自分の子供がそうなってほしい親御様であれば話が違います。
ニューズウィークを普通に読めるような状態にまで持っていく必要があります。
ではどうやって読めばよいのでしょう。
読んだ後の自分の姿を想像する
第一線で活躍する人が読む雑誌です。すべて読んで内容を把握すれば、少なくともその辺にいる周りの人や友人よりも、「世界」を把握できるでしょう。
また、国内メディアが取り扱っていない記事、観点は、他人と異なる、質の良い発想につながるでしょう。
他人に話して違いを見せつける
読むだけではもったいない。
他人に話して、アウトプットすることで、雑誌を読んだ価値が高まります。
恐らくニューズウィークで取り扱う記事は、どれをとっても国内メディアが取り扱っていないので、逆に最初は自分に興味のある記事だけ見ればいいのです。
私も見つけてみました。
・テクノロジー ITの巨人たちと政府の戦いが始まる
・風刺画で読み解く「超大国」の現実 乱射魔の息子を生んだ仰天教育
・人生相談からアメリカが見える 友人や子供の友達にプチ旅行をおごりたい
・テクノロジー ITの巨人たちと政府の戦いが始まる
→ヨーロッパでは、グーグルやアップル、フェイスブック、アマゾン(GAFA)が行っているデータ収集とその利用・運営方法について捜査している。自社のECで有利になるような運用・消費者データ不適切収集、脅威になりそうな会社の買収で競争阻害を行っているのではないか、という疑いがあるということです。今までにEUは反トラスト法(独立禁止法違反)で100億ドル近くをグーグルに制裁金として支払わせているようです。
気になったのは日本で、独立禁止法はあるけど、そんな高額な制裁金を課したのは聞いたことがありません(もしかしたら知らないだけかも)
私にとって重要だったのは、「日本でも同様の動きがあるかも」という気付きを得られたことです。今までの私は、このような話題を振られても何も回答できなかっただろうし、超巨大企業が独立禁止法に対応するために動くことは、多少なりとも仕事にかかわってくると思われました。例えばGAFAの中のサービスで、他社を制限するような仕様や制限があった場合、それがなくなって便利になったり、もしくはその動きに合わせてシステムの切り替えや変更が発生することが見込まれるからです。でも客先や上司との会話で「EUの反トラスト法がまたやりましたね」なんていうと、ちょっと勇み足か。
・風刺画で読み解く「超大国」の現実 乱射魔の息子を生んだ仰天教育
→お笑い芸人でもあるパックンが担当された回です。
乱射事件を起こした子供の親がまずクリスマスプレゼントに銃をプレゼントしています。日本人では考えられないですが、それはとても多いことのようです。しかし、その後がまずい。ピストルや弾丸、出血した死体などの絵、そして「考えるのを止められない。助けて」の文章が見つかり、親が緊急呼び出しを受ける。しかしその後、銃を持ったままの状態で学校に送ってしまう!
そして実際に乱射事件が起きたあと、それを聞いた母は、息子に安否確認ではなく「イーサン、やらないで」、そして父は乱射しているのは自分の息子かもしれないと警察に連絡したそうです。
普通であれば怒ってもおかしくないところですが、この記事の著者のコメント
クランブリー夫妻、悪い親グランプリを取れそう。
経済大国、世界1位の国では子育てに問題があると、日本以上に問題が大きくなるようです。経済的に豊かな国でも、子供の子育て問題はあるんですね。
・人生相談からアメリカが見える 友人や子供の友達にプチ旅行をおごりたい
→読売新聞の「人生案内」が好きです。
ネットでも読めますが回答者の回答がみれない、、、回答者の親身な回答、子気味な回答が楽しみです。
海外版「人生案内」はどうでしょう。
私たち夫婦はそれぞれ高給の仕事についていて、町の平均所得の10倍の収入があります。(中略)車で数時間の観光地に短期滞在するなどミニ旅行をしています。そこで友人たちや、子供たちの友達を招きたいのですが(そのほうが楽しいので)、よその家庭は同じレベルのお返しができないからと、招待を受けるのを躊躇するのではないかと思います。そんなことは全く期待していないのですが、相手に気まずい思いをさせすに、誘いを受けてもらうにはどうすればいいでしょう。
狙って書いてきたかと思うほどの、一般人の心を逆なでするような内容です。
自分が高いところにいて、一般人を見下していることがわかっていないご様子の投稿者。
自分が楽しいので、旅行プレゼントを受け取ってほしい、と。
これ以上書くと冷静でいられなくなりそうなので、ニューズウィークの人生相談員の回答を見てみます。
夕食をおごるのと、休暇を「おごる」のとでは訳が違います。まずは小さく始めましょう。例えば、遊園地のプラチナパスを入手したから、いっしょに行けるなら無料で上げると申し出ます。相手が躊躇したら、彼らとの友達関係を大切に思って、ぜひ一緒に楽しみたいのだと伝えましょう。そして一緒に遊園地に行くことになった時、彼らが昼食代を負担するとか、みんながジェットコースターに乗っている間に子供たちを見ているなど、お礼の気持ちを示そうとしたら、快く受け入れましょう。(中略)
完璧だ
具体的な例も出して、というかもうこの案で行ったほうがいいぐらい。
招待された人がお返ししてくる可能性も気づき、「投稿者はきっと断っちゃう。ちゃんと受け入れるように言っておかないと」というフォローもばっちり。
日本でこのような人はいるのかな、、、海外だけなのか。
でも「本当にお返しを求めないプレゼント」をどうやって渡すのか、は日本でも難しい問題ですね。
最後に
ニューズウィークは、中国やアメリカ、ヨーロッパ・中東など、様々な国と地域のニュースを扱いますが、どれも身近な内容ではないので読んでいてもわからない事ばかり。
しかし、わかる記事もあるので、まずそこから見るようにして、少しずつ海外のニュース記事をみるよう、時間をかければ少しずつ慣れていけそうです。
幸い、
dマガジン であれば、過去のバックナンバーも気軽に見ることができるので、2か月ぐらい前の記事も簡単に見ることができます。
もし、暇な時間にネットニュースやYoutube,漫画などを見て、「時間無駄にしちゃったな」と思われる方がいれば、ぜひ
dマガジン でニューズウィークを読んで、質の良い日本語をどんどん読んでいきましょう。